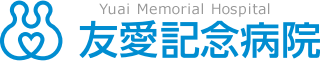#31:レセプト診査の理不尽
この文章は平成22年1月に発行された茨城県病院協会報●●号に書いた文章です。
レセプト診査の理不尽
院長 加藤奨一
約10年前、私がまだ病院長ではなく外科部長だった頃、こんなことがありました。
患者さんは60歳代の男性でした。閉塞性黄疸で入院となり、各種精査の結果、肝門部胆管癌の診断となりました。PTCD(経皮経肝胆道ドレナージ)を行い、減黄を待って手術しようということになりましたが、癌の浸潤部位が上部胆管から左右肝管に及んでおり、胆管切除断端の癌陰性という手術の根治性を求めると「肝右3区域切除」(外側区域のみ残し、内側区域を含んだ肝臓の右側を7割程度切除する術式)が必要なため、残肝ボリュームをなるべく大きくし、術後肝不全を防ぐために、手術に先行して門脈右枝の塞栓術を行い、左葉の代償性肥大を待ってから肝切除に臨みました。
手術は予定通り順調に終了し、胆管切除断端も癌陰性でしたが、翌日から総ビリルビンが上昇し始めました。拡大右葉切除や右3区域切除といった大量肝切除後には残肝のボリュームがかなり小さくなるため、一定頻度で「術後肝不全」が起こり得ます。不幸にもこの患者さんは「術後肝不全」になってしまったのです。これを乗り切るには、残肝が肥大し、肝機能が生命維持に足りるだけに回復するまで「血漿交換」を繰り返すしかありません。血漿交換を開始しました。
1回の血漿交換の直後には総ビリルビ値もアンモニア値も下がりますが、1日経つと再上昇を始めるため、ほぼ1日毎に血漿交換が必要でした。多少の肝性脳症の傾向はあったものの、患者さんの意識状態は良好であり、ご家族や我々医療者とも十分なコミュニケーションが取れる状態でした。
そうこうしているうちに血漿交換も7回を数えました。ここで大きな問題が発生しました。「術後肝不全に対する血漿交換は7回を限度とする。」という保険診療上の制約があります。ご家族と話し合った結果、その後の血漿交換は自費となってもいいから続けて欲しいというお返事をいただき、その後も血漿交換を繰り返す毎日が続きました。
血漿交換は血液透析と同じように、患者さんにとってはとても身体的にしんどいようで、27回を過ぎたところで、患者さんご自身から血漿交換の中止を求められました。ご家族も本人の意志を尊重したいとの意向でしたので、やむなくその時点で血漿交換を終了しました。当然、その後は肝不全が徐々に進行し、術後約2ヶ月後に患者さんはお亡くなりになりました。
この患者さんは大変体格のよい方で、1回の血漿交換に新鮮凍結血漿が35単位ほど必要でした。金額にすると1回あたり30万円ほどかかることになり、保健適応外の血漿交換の費用が600万円を越えました。ご家族とは血漿交換が8回目を迎える時点で自費で行うとの合意がありましたが、患者さんが最終的にお亡くなりになられたため、人道的見地から自費の徴収は取りやめ病院負担とすることにしました。
臨床経過から言って、血漿交換が7回を越えたことは当然のことであり、私は今回はぜひ公費負担を認めるべきだと考えました。1ヶ月の医療費がこれほどの高額になった場合、症状詳記も1日1ページの詳細な経過報告書が必要になります。患者さんのご冥福を祈りつつ、私は一生懸命60ページにわたる症状詳記を書きましたが、私の希望とは裏腹に、血漿交換の27回中20回は保険適応外との返答が返ってきました。すぐに再診査請求もしましたが、これもあえなく突っぱねられ、結局病院が600万円以上を負担するということになりました。
「臨床的に現場で必要な医療」と「公的負担を認める医療」とのギャップを痛感した一件でした。外科医であれば誰でも術後在院死亡した患者さんを何人かは経験しており、こうした患者さんのことは一生忘れないのですが、レセプト診査の一件とも相まって、この患者さんは私にとっては外科医として一生忘れられない患者さんとなっています。
さて、最近もこうした「レセプト診査の理不尽」を感じる機会が多くなりました。
つい先日ですが、医事課の職員から「総胆管結石症の術前検査に造影CT検査がされているが、その必要性を説明せよ、との要求が来ている。」と連絡をもらい、私は激怒しました。
胆嚢内結石や総胆管結石の診断だけならエコー検査だけでもできるかもしれませんが、手術の安全性を可能な限り高めるためには、現代医療が提供できるポピュラーな検査法であれば、可能な限り術前に行い、情報を得ておくことが大切です。胆道結石症の手術をするのであれば、MRCPによる胆道系精査やCT検査による胆道系の把握や他臓器の情報収集は、外科医が手術をより安全に行うためには、緊急性が高くて実施している時間的余裕がないなら別ですが、予定手術の前にはぜひ実施しておくべき検査であり、決して不必要な無駄な検査ではありません。また、CT検査も単純撮影だけでなく造影剤を使用した撮影を加えることは、診断能を飛躍的に高めます。ある放射線科医は「診断能の落ちる単純CTで病変を見逃し、異常なし、と安心してしまうくらいなら、造影CTではないCT検査は行わない方がよいくらいだ。」と言っています。こうした検査を不必要な無駄な検査のように言ってくることは全く信じがたいことでした。「診査される方の診査能力の無さを教えてくれるような、恐ろしい問い合わせです。」とちょっとした皮肉を交えてこちらからお返事しました。
最近うちの病院のある医師は症状詳記の中で、「今回の治療、薬剤の使用方法について疑問があるなら、現場に来て実際に患者を診て下さい。そうすれば、お気軽にカットなどできないはずです。」と書いていましたが、臨床の現場で一生懸命に患者さんの救命をしようと頑張っている医師であればあるほど、こうした憤りを感じるのではないでしょうか。
以前ある医師の方がその著書の中でレセプト診査について、「『診査(査定)』と言えば聞こえはいいですが、学問的な裏付けはなく、治療上の必要性や、医師の人道的使命感を全く評価しません。都道府県ごとで基準が違い、年度でも基準が変わり、一定していません。『カット屋』と言われる専門業者を雇い、『今月はこの項目とこの項目をカットし、全体で何%医療費を削減しよう。』と、その時の気分次第で医療費の支払いを拒否します。あまりにも理不尽な支払い拒否に対しては病院から抗議しますが、病院からの抗議には耳を貸さず、結局病院が泣き寝入りをすることがほとんどです。このレセプト診査とは、『適正医療』の名を借りた、一方的な医療費の“踏み倒し” “食い逃げ”行為だと思います。本来健康保険組合は、自分たちで漏れなく保険料を集め(未徴収率が高いのが問題になっています)、自分たちで赤字を解消するべきなのに、医療機関に責任を転嫁し、『病院が故意に過剰診療をし、暴利を得ている』というイメージ・キャンペーンを繰り返しています。マスコミも、これを鵜呑みにし、査定部分を『過剰診療』と表現し、患者側の誤解を招いています。」と辛口のコメントをされていましたが、その通りだと思います。
診療報酬制度を語るときよく「支払い側」「医療側」という言い方をします。「支払い側」は健保組合、「医療側」は医療機関を指しているわけですが、よく考えてみると、医師や医療機関は患者さんの代理として患者さんの代わりに、行った(受けた)医療行為に対する公費負担を請求しているわけで、本当は「患者側」なのではないでしょうか。そう考えると、むやみやたらに公費負担を「カット」することは、患者さんの公的医療を受ける権利を侵害していることになります。「支払い側」が患者さんの公的医療を受ける権利を侵害し、自分たちの義務を履行しない、そのツケを医療機関に押しつけているだけだということになります。
医師であれば誰もが「レセプト診査の理不尽」を感じていながら、文句も言えない状態が何十年も続いています。ここらへんで、制度自体を考え直してはどうでしょうか、患者さんの公的医療を受ける権利を守るために。
長い自民党政権が終わり、民主党が政権を取りました。医療制度や診療報酬制度を大きく変えるチャンスです。「医療崩壊」は、小松秀樹先生や本田宏先生を中心とした多くの医師達の悲鳴にも似た訴えが功を奏して、国民の多くに周知されました。今度はぜひこの「レセプト診査の理不尽」も国民的議論のテーマに上がるよう、医師達が立ち上がったらどうでしょうか。
「患者さんが公的な医療を受ける権利を患者さんに変わって主張」する立場にある者として、そんなことを思っている今日この頃です。